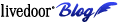2005年08月28日
すりきれたビデオテープ
歳月を経ても色褪せない文章がある。そのなかのひとつで折りにふれ甦るのが、小田昭太郎の「ビデオテープの再生とボクの再生」である。季刊「いま、人間として」創刊第二巻(径書房・1982/9/20)に収められているわずか2ページの一文だが、内容が異彩を放つ。
以下、本文を要約しながら、引いてみる。
小田氏はTV制作現場にいるディレクター。7年まえに取材し、放送した番組「俺たちはロボットじゃない」の当事者である長崎さん(東京の下町にある製瓶工場の組合の副委員長)からの電話に、小田氏は衝撃を受ける。
取材した当時、その製瓶工場は東京都から多額の助成金を貰い、労働大臣賞を受賞している身障者雇用の福祉モデル工場だった。180名の従業員のうち、106名が心身障害者。しかし実際は、身障者はひどい差別を受けていた。給与や待遇面ばかりではなく、言葉の暴力もあった。
長崎さんたちはその差別と偏見に抗議し、命がけで組合を結成。参加したのは36名。そのうち精薄者23名、身障者10名、健常者は長崎さんを含む3名のみ。一般従業員組合との給料格差や差別をなくすよう会社と団交を重ねた。
小田氏は36名の闘いの結果、彼らの要求を会社側が認める時点までを取材し、放送した。
長崎さんの電話の用件は、放送された「俺たちはロボットじゃない」をビデオに収録し、繰り返し見ているうちにビデオがすりきれてしまい、とうとう映らなくなってしまったが、なんとかならないか、ということだった。
《「すりきれてしまって……」という一言が、グサリ、胸に突き刺さった。一も二もなく、なんとかしましょうと答えた。方法はある》
すぐに彼から手紙が届き、同封された資料を読んで、小田氏はとことんまで打ちのめされる。それはこの7年間の彼らの組合闘争の記録だった。放送後、すぐに会社側は激しい組合つぶしを行っていた。「福祉モデル工場」の看板はさっさと取りはずし、多くの障害者や精薄者を解雇した。組合員が14名に減っても、長崎さんたちは、5件の裁判をかかえ、会社と闘い続けていた。
《しかし一方、取材した側のボクはといえば、取材後の七年間、電話があるまで長崎さんたちのことを考えたことがなかった。本当は認めたくないのだが、ボクの気持ちの中で「この問題はこれで終り」と勝手にケリをつけてしまっていたことはたぶん事実なのだろう。そんな自分が恥かしいし、長崎さんたちに対して何とも申し訳のない気持になってしまう。しかし、それにも増して考え込んでしまうのは、結局、ボクたちは七年前、一体何を取材し、何を放送したのかということについてである》
小田氏は、長崎さんと委員長の杉田さんたちに会う。
脳性麻痺障害者の杉田さんは放送の夜、一晩中号泣し続けたという。それは画面の中の自分がそれまでの人生で初めて人間として扱われていたからだった。
《ボクたちドキュメンタリー制作者は、表面的な出来事だけに惑わされず日常の中に埋もれている恐ろしさをみつめていきたいと常々考えてきた。しかしボクは、杉田さんたちの沈黙の日々については何の記録もしていない。その沈黙の日々の中で杉田さんたちは、自分たちの内なる差別意識に気づいていった》
この「内なる差別意識」というのは、「健常者から差別された心身障害者の仲間同士の間での差別」を指す。二重、三重の差別構造である。
小田氏は文末をこう結ぶ。
《いまにしてようやくボクはこの人たちの痛みと闘いの意味に気づいた。七年前、ボクは一体何を取材し、何を放送したというのだろうか――》
現実的な問題として、取材者側が小田氏の問うているレベルまでこだわって仕事をすることは不可能であろう。しかしそのことにこだわりつづける限り、番組制作者の視点はぶれないし、なんらかのかたちで番組に反映されると信じたい。
取材した他者が制作者のなかで自己完結することの危うさを、小田氏は訴えているように思える。
これを視聴者の立場で考えると、どういうことになるのか。
あるドキュメンタリー番組を観て感銘を受ける。それをいちいち血肉化させる努力をしていては、正直なところ身がもたない。自分の体験できない世界、知らなかった世界、これから考えてゆくべきテーマ、それらを引きずったまま生きてゆくしかないと思う。
しかしそのような番組も、近頃めっきり少なくなった。
番組のむこう側に存在する制作者に想いを馳せるという意味で、わたしにとって小田昭太郎は忘れがたい人物である。彼を知る人物を2人知っているが、「男が惚れる男」であるように感じた。
小田氏がこの一文を記してから23年が経過した。
彼はいま、どのような地点に立っているのだろうか。
(つづく)
以下、本文を要約しながら、引いてみる。
小田氏はTV制作現場にいるディレクター。7年まえに取材し、放送した番組「俺たちはロボットじゃない」の当事者である長崎さん(東京の下町にある製瓶工場の組合の副委員長)からの電話に、小田氏は衝撃を受ける。
取材した当時、その製瓶工場は東京都から多額の助成金を貰い、労働大臣賞を受賞している身障者雇用の福祉モデル工場だった。180名の従業員のうち、106名が心身障害者。しかし実際は、身障者はひどい差別を受けていた。給与や待遇面ばかりではなく、言葉の暴力もあった。
長崎さんたちはその差別と偏見に抗議し、命がけで組合を結成。参加したのは36名。そのうち精薄者23名、身障者10名、健常者は長崎さんを含む3名のみ。一般従業員組合との給料格差や差別をなくすよう会社と団交を重ねた。
小田氏は36名の闘いの結果、彼らの要求を会社側が認める時点までを取材し、放送した。
長崎さんの電話の用件は、放送された「俺たちはロボットじゃない」をビデオに収録し、繰り返し見ているうちにビデオがすりきれてしまい、とうとう映らなくなってしまったが、なんとかならないか、ということだった。
《「すりきれてしまって……」という一言が、グサリ、胸に突き刺さった。一も二もなく、なんとかしましょうと答えた。方法はある》
すぐに彼から手紙が届き、同封された資料を読んで、小田氏はとことんまで打ちのめされる。それはこの7年間の彼らの組合闘争の記録だった。放送後、すぐに会社側は激しい組合つぶしを行っていた。「福祉モデル工場」の看板はさっさと取りはずし、多くの障害者や精薄者を解雇した。組合員が14名に減っても、長崎さんたちは、5件の裁判をかかえ、会社と闘い続けていた。
《しかし一方、取材した側のボクはといえば、取材後の七年間、電話があるまで長崎さんたちのことを考えたことがなかった。本当は認めたくないのだが、ボクの気持ちの中で「この問題はこれで終り」と勝手にケリをつけてしまっていたことはたぶん事実なのだろう。そんな自分が恥かしいし、長崎さんたちに対して何とも申し訳のない気持になってしまう。しかし、それにも増して考え込んでしまうのは、結局、ボクたちは七年前、一体何を取材し、何を放送したのかということについてである》
小田氏は、長崎さんと委員長の杉田さんたちに会う。
脳性麻痺障害者の杉田さんは放送の夜、一晩中号泣し続けたという。それは画面の中の自分がそれまでの人生で初めて人間として扱われていたからだった。
《ボクたちドキュメンタリー制作者は、表面的な出来事だけに惑わされず日常の中に埋もれている恐ろしさをみつめていきたいと常々考えてきた。しかしボクは、杉田さんたちの沈黙の日々については何の記録もしていない。その沈黙の日々の中で杉田さんたちは、自分たちの内なる差別意識に気づいていった》
この「内なる差別意識」というのは、「健常者から差別された心身障害者の仲間同士の間での差別」を指す。二重、三重の差別構造である。
小田氏は文末をこう結ぶ。
《いまにしてようやくボクはこの人たちの痛みと闘いの意味に気づいた。七年前、ボクは一体何を取材し、何を放送したというのだろうか――》
現実的な問題として、取材者側が小田氏の問うているレベルまでこだわって仕事をすることは不可能であろう。しかしそのことにこだわりつづける限り、番組制作者の視点はぶれないし、なんらかのかたちで番組に反映されると信じたい。
取材した他者が制作者のなかで自己完結することの危うさを、小田氏は訴えているように思える。
これを視聴者の立場で考えると、どういうことになるのか。
あるドキュメンタリー番組を観て感銘を受ける。それをいちいち血肉化させる努力をしていては、正直なところ身がもたない。自分の体験できない世界、知らなかった世界、これから考えてゆくべきテーマ、それらを引きずったまま生きてゆくしかないと思う。
しかしそのような番組も、近頃めっきり少なくなった。
番組のむこう側に存在する制作者に想いを馳せるという意味で、わたしにとって小田昭太郎は忘れがたい人物である。彼を知る人物を2人知っているが、「男が惚れる男」であるように感じた。
小田氏がこの一文を記してから23年が経過した。
彼はいま、どのような地点に立っているのだろうか。
(つづく)
miko3355 at 16:17│TrackBack(0)│小田昭太郎にまつわるページ
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by 念仏の鉄 2005年08月30日 11:38
メディアを生業とする者にとっては、身につまされる話です。
(そうでないとしたら、その人はいささか危なっかしい)
「黒田軍団」と讚えられた時期の読売新聞大阪社会部長だった黒田清さんは、ある時期に「これからは読者とともに生きていく」と宣言して会社をやめ、「窓友新聞」というミニコミ新聞を創刊しました。
それもひとつの答えだとは思います。
しかし、そこまでの思い切りのない者は、関わった人たちのその後を、宿題として抱えながら歩いていくしかないのでしょうね。
(そうでないとしたら、その人はいささか危なっかしい)
「黒田軍団」と讚えられた時期の読売新聞大阪社会部長だった黒田清さんは、ある時期に「これからは読者とともに生きていく」と宣言して会社をやめ、「窓友新聞」というミニコミ新聞を創刊しました。
それもひとつの答えだとは思います。
しかし、そこまでの思い切りのない者は、関わった人たちのその後を、宿題として抱えながら歩いていくしかないのでしょうね。
2. Posted by miko 2005年08月31日 08:02
念仏の鉄さま
コメントいただきありがとうございます。思いがけないことでしたので、うれしく思います。
先日の一件では、ほんとうに失礼いたしました。
文章表現には留意しているつもりでしたが、むずかしいですね。
そんなわけで、意気消沈しながら本エントリーを書きました。
黒田清にはわたしも注目していました。やさしい眼をしていましたが、眼に光がありました。一方、大谷昭宏はやさしいだけの眼になってしまい、残念に思っています。
鉄さんのblogのコメント欄が、複数の閲覧者による「情報の共有と活性化」が具現化されますよう念願しています。コメント欄は、運営者の資質の反照だと思えるからです。
コメントいただきありがとうございます。思いがけないことでしたので、うれしく思います。
先日の一件では、ほんとうに失礼いたしました。
文章表現には留意しているつもりでしたが、むずかしいですね。
そんなわけで、意気消沈しながら本エントリーを書きました。
黒田清にはわたしも注目していました。やさしい眼をしていましたが、眼に光がありました。一方、大谷昭宏はやさしいだけの眼になってしまい、残念に思っています。
鉄さんのblogのコメント欄が、複数の閲覧者による「情報の共有と活性化」が具現化されますよう念願しています。コメント欄は、運営者の資質の反照だと思えるからです。